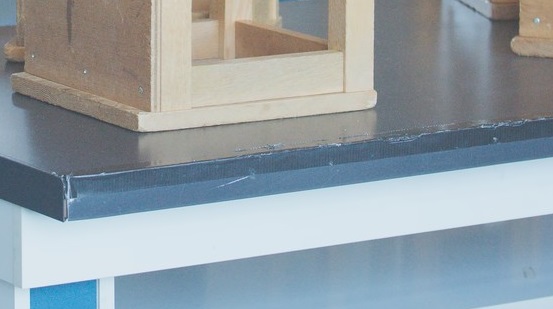小説としては小品である『時をかける少女』は、映像作品で成功し、作品世界を広げている。映画、ドラマ、アニメと映像作品に恵まれた。
最初の映画『時をかける少女』は、二つの流れで説明できる。一つは角川映画としての流れ。角川書店のメディアミックス戦略により、小説から映画へというだけではなく、女優の売り出しや主題歌の露出などで相乗効果をあげていた。もう一つは大林宣彦監督作品としての流れ。映画版は尾道三部作の一作としても数えられる。キャストは良くいって初々しいが、作品全体のクオリティー維持には大林監督の手腕が光る。この映画の絵としての良さは舞台を尾道にしたことの効果が大きい。
細田守監督によるアニメ版も有名になった。こちらはこれまでの『時をかける少女』作品群のオマージュとして作られたとみることもできる。
原作小説は、ジュブナイルと呼ばれる新しいジャンルで呼ばれた。juvenileは少年向けという意味で、英語圏でも存在する括りである。ジュブナイルという言い方そのものはあまり流行らず、現在ではヤングアダルト(YA)という言い方も一般化している。ヤングアダルトが市場として意識的にターゲットされたのは本作発表よりもっと後、80年代以降だと考えられる。この流れはのちにライトノベルと呼ばれる一群を生む前段階であった。
本作は時間跳躍の理由づけに科学をもちだしている。いちおうはこれをもってSFとするしかない。SFとファンタジーは扱うギミック・道具立てがちがうだけで、実際多くの作品群がもつ構成・構造はよく似ている。ジャンルがそうなのだから、一作品である『時をかける少女』についてSFかファンタジーか問うことにはあまり意味がないかもしれない。ファンタジーだと言ったっていいのである。そしてそれが尾道と相性がよかった理由でもある。
この小説で大切なのは青春小説という側面だ。そこをはずすと『時をかける少女』でなくなってしまう。逆を言えば、そこさえおさえれば『時をかける少女』らしさを失わずにアレンジした映像化もできるということだ。この話は少女の短い夢であると言うこともできる。もちろんこれは、夢オチにしても同じことだとかそんなことが言いたいのではない。本作においてなにより大事なのは、一人の女が「少女」というとりもどせない短い時間を生きていることにある。この小品が永遠の青春小説として残るのは、「少女」とは過ぎ去る時間の容赦のなさに気付き始めているものだからだ。
細田アニメ版の「未来で待ってる」というセリフと、大林実写版の「時間は過ぎていくんじゃない。やってくるものなんだ」というセリフは呼応していると思う。いつか何かがやってくるという予感の大切さ。それは原作小説のラストからちゃんと引き継いでいるものなのである。小説ではその予感を主人公が自発的にもち、映像作品では恋した男が示唆するという違いだけがある。
今となっては、恋愛要素のある学園ものと時間跳躍は、準古典的モチーフとなっている。作者だって執筆時に予感しなかったであろうことは、小品『時をかける少女』が数々の派生作品のインスピレーションの源となり、まさに時を駆けていくことになる未来だろう。